文書の過去の版を表示しています。
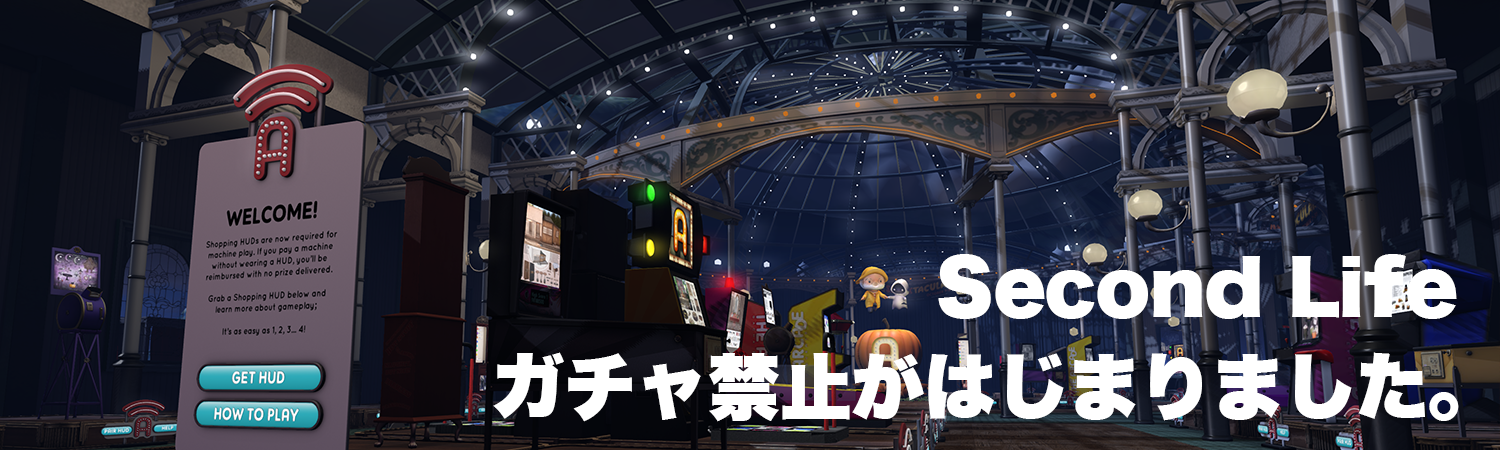
ガチャに関するまとめ(ガチャポリシーの変更と影響)
2021年9月から、ガチャ(ルートボックス)がSecond Life内で禁止されました。しかし、2024年10月9日に規制が見直され、ガチャが再び利用可能となりました。この変更には「譲渡不可」の新しいルールが導入されており、購入したガチャアイテムを他のユーザーに譲渡することができなくなっています。詳細は「ガチャポリシー」、Second Life公式ブログの「2024年のガチャポリシー変更のお知らせ」をご覧ください。
どうしてガチャ規制が必要?
ガチャ規制は、ゲーム業界全体のガチャ自主規制の流れに沿ったものでした。特に未成年への影響やギャンブル性が問題視されています。
アメリカではルートボックスに関する統一された連邦法は存在していませんが、一部の州で未成年がガチャやルートボックスにアクセスできないようにする規制が提案されています。また、欧州連合(EU)などでは、ルートボックスのギャンブル性に対する厳しい規制が導入されており、ベルギーやオランダなどはルートボックスをギャンブルと見なして完全に禁止しました。
日本でもガチャに関する問題は注目されており、特に「コンプガチャ」が景品表示法に違反する可能性があるとして2012年に自主規制が行われました。また、ゲーム業界団体によって確率の表示や未成年の課金制限などがガイドラインとして設けられています。
Second Lifeでも、ユーザーの安全を守り、クリエイターの権利を保護するため、2021年9月にガチャを禁止しました。しかし、2024年に規制が緩和され、新たなルールを設けることでガチャが再導入されています。
2024年の規制緩和と新しいルール
2024年10月9日、ガチャに関する規制が見直され、再び利用可能となりました。この変更により、ガチャアイテムには以下の2種類が存在することになりました:
譲渡可能なガチャアイテム
- 2021年からの規制で、譲渡可能なガチャアイテムは「コンベヤベルトシステム」でのみ販売可能です。
- 過去に取得したこれらのアイテムは、マーケットプレイスやヤードセールでの再販売が引き続き許可されています。
譲渡不可のガチャアイテム
- 2024年の規制緩和により、新たにガチャが利用可能となりましたが、これらのアイテムは譲渡不可です。
- クリエイターは以前のようにランダム要素を用いたガチャ方式で販売できますが、購入したユーザーが他者に譲渡することはできません。
この変更の目的は、以下の通りです:
- クリエイターの権利保護: 転売によってクリエイターの収益が第三者に渡る問題を防ぎ、クリエイターの努力が正当に報われる環境を作る。
- 詐欺行為の防止: 譲渡可能なガチャアイテムは詐欺に悪用される可能性がありましたが、譲渡不可とすることでリスクを軽減。
- ユーザーの安心: 詐欺のリスクが減ることで、ユーザーは安心してガチャを楽しむことができます。
この新しいルールにより、ガチャの健全な利用が促進され、ユーザーとクリエイターの双方にとってより良い環境が提供されることを目指しています。
過去のガチャアイテムの利用と新しいガチャ販売方法
過去に取得した譲渡可能なガチャアイテムについては、引き続きマーケットプレイスやヤードセールなどでの販売が可能です。ただし、新たに取得するガチャアイテムについては「譲渡不可」のルールが適用されており、他のユーザーに渡すことはできません。以下はガチャアイテムの利用や販売に関する情報です:
- 過去の譲渡可能なガチャアイテムはマーケットプレイスやヤードセールなどで販売が可能です。
- 新たに取得したガチャアイテムは「譲渡不可」であり、ユーザー間での取引はできません。
新しいルールによって、クリエイターが安心してアイテムを提供できる環境が整い、ユーザーにとっても詐欺リスクの少ないガチャ体験が提供されることが期待されています。
コンベヤベルトシステムによるガチャ販売

日本ではD-Labの機械「みえぽん」が有名です。リンク先はFlickr、販売は店舗のみ。
コンベヤベルトシステムでは、過去に取得した譲渡可能なガチャアイテムを販売することが可能です。このシステムは今後、譲渡可能な状態での販売を可能にする唯一の方法として許可され続けると考えられます。購入者が事前に確認した上でアイテムを購入することができ、安心して取引が行える仕組みとなっています。
The Arcadeは独自のコンベヤベルトのHUDを使用して購入します。(HOW TO PLAYで解説)
釣りゲーム・動物繁殖系は対象外です
7seasやKittycatsのようなシステムは影響を受けません。現時点では、ゲーム性が強いものは規制の対象外です。
ガチャ禁止による影響と規制緩和後のメリット
購入者にとって、ガチャ禁止による直接的なデメリットは少なく、むしろメリットが多いとされています。購入手順が変更され複雑になる部分もありますが、詐欺リスクの軽減やクリエイターの権利保護といった利点があります。
クリエイターが新しい流れに乗れないと売上が減少する可能性もありますが、適切に対応することで全体としてメリットを享受することができます。変化についていけないクリエイターは市場から姿を消すことになるかもしれませんが、長期的にはこの規制緩和により健全な市場が形成されると期待されています。